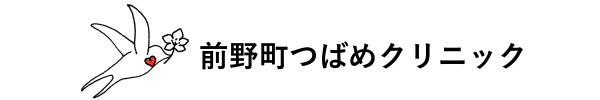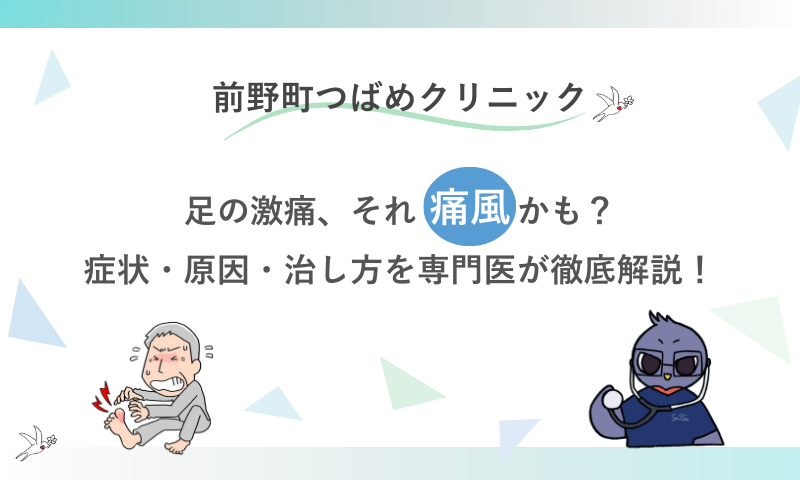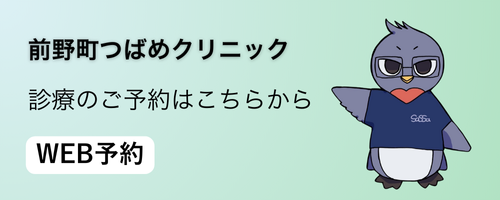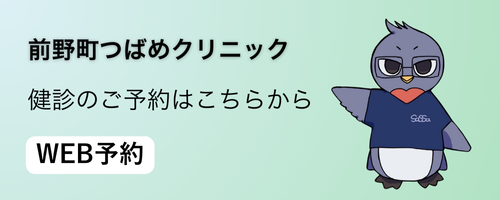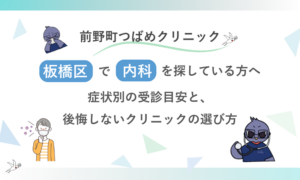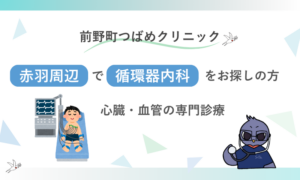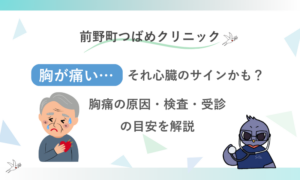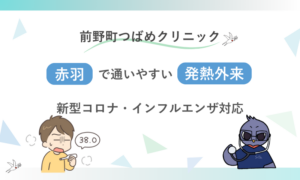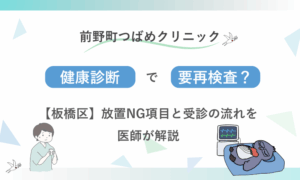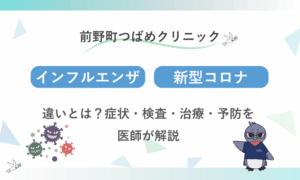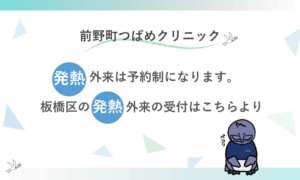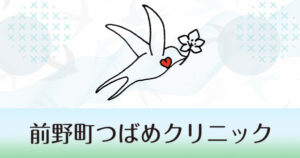「足の親指の付け根が、突然ズキズキと痛み出した」
そんな激痛に見舞われた経験はありませんか?
特に朝方や夜中に痛みで目が覚める、歩くのもつらいほど腫れている……。
このような症状は、単なる関節痛ではなく「痛風」の発作かもしれません。
痛風は、体内の尿酸が結晶化して関節に炎症を引き起こす病気で、発作時には耐えがたい激痛を伴います。



放置してしまうと、発作の再発を繰り返すだけでなく、腎臓や血管にも悪影響を及ぼし、高血圧・腎機能障害・動脈硬化といった合併症のリスクも高まります。
この記事では、痛風の症状や原因、治療法、そして日常生活でできる予防策までを専門医の視点からわかりやすく解説します。
「これって痛風かも?」と不安な方、過去に発作を経験したことがある方は、ぜひ参考にしてください。
当院では、今症状がある方はもちろん、この先の不安や、過ごし方に迷う方も、当院でゆっくりと話して、少しでも安心を得ていただけるよう気軽になんでも相談していただける雰囲気づくりを心がけております。
【板橋区】前野町つばめクリニック院長



痛風の基本的な仕組み
痛風とは、体内で尿酸という老廃物が過剰に蓄積し、血液中の尿酸値(尿酸値:mg/dL)が高くなることで関節に炎症が起こる病気です。
特に血中の尿酸濃度が高くなると、尿酸が結晶化して関節に沈着し、免疫反応によって激しい炎症を引き起こします。
この炎症による突然の激しい関節痛が「痛風発作」と呼ばれるもので、多くの人が「風が当たるだけでも痛い」と表現するほどの強烈な痛みが特徴です。
発症しやすい部位とタイミング
痛風発作が最も起こりやすい部位は、「足の親指の付け根(第一中足趾関節)」です。特に朝方や夜間、身体が冷えている時間帯に突然腫れと激痛が出現し、歩行が困難になるほど腫れ上がることもあります。
そのほか、足首・膝・かかと・手指などにも発作が起きることがありますが、いずれも片側の関節に発生するのが特徴です。
痛風発作と高尿酸血症の関係
痛風は、発作が起きているときだけが病気ではありません。実は、症状がない状態でも血中の尿酸値が高い状態を「高尿酸血症(Hyperuricemia)」と呼び、これが長く続くことで痛風発作や腎臓の機能低下、尿路結石などの合併症を招きます。
特に男性では、30代以降から尿酸値が高くなりやすく、健康診断で「尿酸値7.0mg/dL以上」と指摘された場合は、将来的な発作や腎障害のリスクが高まります。
この数値は、日本痛風・尿酸核酸学会のガイドラインでも「治療開始の目安」として明確に定められています。
https://www.tukaku.jp/guideline/


足の親指に突然の激痛—痛風発作の典型症状
痛風発作の代表的な症状は、足の親指の付け根(第一中足趾関節)に起こる突然の激しい痛みです。
多くの場合、発作は夜間から早朝にかけて始まり、赤く腫れて熱感を伴い、わずかな接触でも強い痛みを感じます。歩行が困難になるほどの腫れが生じることも少なくありません。
このような症状は、体内に蓄積された尿酸が関節内で結晶化し、強い炎症を引き起こすことで発生します。MSDマニュアルでも、「急性の関節痛、熱感、発赤、腫れが突然発症することが典型的で、最初の発作は第一中足趾関節に起こることが多い」と明記されています。
⚠ 発作は片側・急性・再発性
痛風発作は通常、片側の関節に限局して発症します。
初回は足の親指に起こることが多いですが、繰り返すうちに足首、膝、手首などの他の関節にも波及する可能性があります。
発作は突然始まり、痛みは24時間以内にピークに達することが多く、その後1〜2週間で自然におさまることもあります。
ただし放置すると再発の頻度が増し、炎症が慢性化するケースもあります。
前兆や合併症にも注意が必要
発作の前に、違和感や軽いむずむず感などの前兆症状を感じる方もいます。
また、痛風を繰り返すことで、尿路結石・腎障害・高血圧などの合併症が進行するリスクも指摘されています。
そのため、痛風発作が疑われる症状があれば、自然に治まるのを待つのではなく、早期に医療機関で診断と治療を受けることが重要です。



痛風は「高尿酸血症」が原因で起こる
痛風は、血液中に尿酸が過剰にたまり、その尿酸が関節内で結晶化することで発症します。
この「尿酸が多すぎる状態」は高尿酸血症と呼ばれ、痛風の根本的な原因です。
尿酸値が7.0mg/dL以上になると、高尿酸血症と診断され、放置すると痛風や腎機能障害などのリスクが高まります。
尿酸は、体内の細胞や食べ物に含まれる「プリン体」が分解されることで生成されます。つまり、体の中で作られる量と、尿や便から排出される量のバランスが崩れると、尿酸がたまっていくのです。
食生活と生活習慣が大きく影響する
高尿酸血症を引き起こす主な要因には、以下のようなものがあります。
プリン体を多く含む食品の摂取
肉類・レバー・魚卵・干物など
ビールや日本酒などのアルコール類(特にビールはプリン体が多い)
尿酸の排出を妨げる習慣
飲酒(アルコールは尿酸の排泄を抑える)
水分不足(尿量が減ると尿酸排出も減る)
激しい運動や脱水(尿酸値が急上昇)
肥満・メタボリックシンドローム
内臓脂肪が多い人は尿酸の産生も排泄も不利になる
インスリン抵抗性と高尿酸血症は密接に関係
体質や遺伝の影響も無視できない
痛風は、家族歴がある人に多い傾向があることから、遺伝的な体質(尿酸を作りやすい・排出しにくい)も関係しています。また、腎臓の持病がある方や、利尿剤を服用している方は尿酸がたまりやすく、痛風のリスクが上昇します。
さらに、加齢やホルモンの影響で尿酸値が上昇しやすくなるため、中年以降の男性に多く発症するのが特徴です。女性でも閉経後はリスクが上がります。



痛風の診療は「内科」や「整形外科」へ
足の関節に急な腫れや激痛が起きた場合、「何科を受診すればよいのか分からない」という方も多いかもしれません。
痛風の診療は、内科(一般内科・腎臓内科・代謝内科など)が基本ですが、関節の腫れや炎症が強い場合は整形外科やリウマチ科でも対応可能です。
初めての痛風発作が疑われる際には、まず内科で血液検査を受けて、尿酸値や炎症反応の確認を行うのが一般的です。
血液検査で「尿酸値」と「炎症反応」を確認
診断の第一歩は、血液検査による尿酸値の測定です。血清尿酸値が7.0mg/dL以上であれば高尿酸血症とされますが、痛風発作中は一時的に尿酸値が低下することもあるため、数値だけで判断せず全体像を見ることが重要です。
併せて、CRP(C反応性たんぱく)や白血球数の増加など、炎症の有無も確認されます。発作時にはこれらの値が上昇し、体内で強い炎症反応が起きていることがわかります。
関節液の検査で結晶を確認することも
診断が難しいケースでは、関節に針を刺して「関節液」を採取し、尿酸の結晶があるかを顕微鏡で確認することがあります。
これは、関節炎の原因が細菌感染やリウマチでないことを区別するうえでも有用な検査です。
また、痛風に似た症状を引き起こす他の疾患(偽痛風、関節リウマチ、化膿性関節炎など)と鑑別するために、レントゲンや超音波(エコー)検査が行われることもあります。
痛風とわかったら、定期的な尿酸値チェックが重要
痛風は一度発症して終わりではなく、「高尿酸血症の管理を継続して行うこと」が根本治療につながります。
症状が落ち着いていても、尿酸値が高い状態が続いていれば再発や合併症のリスクが残ります。
定期的に血液検査を受けて、尿酸値が6.0mg/dL未満を目安にコントロールしていくことが重要です。



急性発作時は「炎症を抑える薬」が中心
痛風発作が起きたときは、まず激しい痛みと炎症を抑えることが優先されます。治療薬としては以下のようなものが用いられます。
NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)
例:ロキソプロフェン、インドメタシンなど。強い痛みを短期間で和らげます。
コルヒチン
発作のごく初期に使用することで炎症反応を抑制。予防投与としても使われることがあります。
副腎皮質ステロイド(内服・注射)
NSAIDsが使えない人(胃潰瘍、腎機能障害など)に対して有効。全身的または局所的に使用します。
なお、発作時には尿酸値を下げる薬(次節で解説)を急に開始・変更しないことが原則です。かえって症状が悪化する恐れがあるため、炎症が収まってから本格的な治療に入ります。
発作が落ち着いたら「尿酸値を下げる治療」へ
再発防止・根本治療のためには、血清尿酸値を6.0mg/dL未満にコントロールすることが目標とされます。この段階で使用されるのが、以下のような尿酸降下薬です。
尿酸生成抑制薬(例:アロプリノール、フェブキソスタット)
→ 尿酸の産生を抑えて、血中濃度を下げる
尿酸排泄促進薬(例:ベンズブロマロン、プロベネシド)
→ 腎臓からの尿酸排出を促進する
薬の選択は、年齢・腎機能・合併症の有無などに応じて医師が判断します。治療を開始したら、月1回程度の採血による尿酸値のモニタリングが推奨されます。
食事・運動・水分管理も不可欠な要素
薬だけではなく、生活習慣の改善も痛風治療の重要な柱です。以下のような対策が効果的です。
食事
プリン体を多く含む食品(レバー・魚卵・干物・アルコールなど)を控える
野菜・海藻・乳製品などを意識的に取り入れる
過度な糖質や脂質の摂取を避ける
体重管理・運動
肥満は高尿酸血症のリスク因子
軽めの有酸素運動(ウォーキングなど)を無理なく継続
水分摂取
1日2Lを目安に水分補給
尿量を増やすことで尿酸の排泄を促進
「薬+生活習慣改善」の継続が再発予防のカギ
痛風は一度治ったように見えても、尿酸値が高いままでは必ず再発します。
治療を自己判断でやめてしまうのではなく、医師の指導のもとで長期的なコントロールを続けることが、再発を防ぎ、腎障害や動脈硬化といった重篤な合併症から体を守ることにつながります。



食事の見直しが予防の第一歩
痛風の最大の予防策は、「血清尿酸値を適正に保つ生活習慣」を継続することです。中でも毎日の食事は、尿酸の産生と排出に大きく関わります。
控えたい食品・習慣
プリン体を多く含む食品(レバー、白子、干物、魚卵、肉の脂身)
ビールや日本酒などのアルコール類(特にビールはプリン体が多く含まれる)
清涼飲料水やお菓子など糖分の過剰摂取(果糖が尿酸値を上げやすい)
取り入れたい食品・栄養素
低脂肪の乳製品(ヨーグルト、牛乳)→ 尿酸排出を促進する働きあり
野菜・海藻・キノコ類 → 食物繊維やカリウムが代謝をサポート
水 → 十分な水分摂取で尿酸の排出を促進
極端な食事制限ではなく、バランスの取れた和食中心の食生活が理想です。
運動と体重管理で「尿酸をためにくい体」に
肥満、とくに内臓脂肪型肥満は尿酸値を上げる要因です。体重の5%程度を減らすだけでも尿酸値の改善が期待できます。
推奨される運動
- 1日30分程度のウォーキング
- 水中運動やストレッチなど、関節に負担の少ない運動
(過度な筋トレやハードな運動は尿酸を一時的に上昇させるため注意が必要)
継続が何より大切です。「無理のない範囲で」「楽しみながら続けられる」ことを意識しましょう。
水分摂取と排尿リズムの整備も大切
水分をしっかりとることは、尿酸を尿からスムーズに排泄させるために欠かせません。特に夏場や運動後は脱水になりやすく、尿酸値が急上昇することもあるため注意が必要です。
水分摂取のポイント
- 1日あたり1.5〜2.0リットルを目安に
- コーヒーや緑茶は利尿作用があるが、カフェイン過剰に注意
- こまめな水分補給を習慣化する
日常習慣を整えることが再発防止につながる
寝不足・ストレス・暴飲暴食は、尿酸の代謝や排出に悪影響を与えます。
規則正しい生活リズム、週に1〜2日の休肝日、食事の「腹八分目」などを意識しましょう。
痛風は「生活習慣病のひとつ」ともいえる疾患です。薬によるコントロールに加えて、こうした日常の心がけが発作の再発予防と合併症リスクの軽減につながります。



前野町つばめクリニックでは、痛風や高尿酸血症に関する診察・検査・治療を幅広く行っています。
「足の関節が腫れて痛む」「健康診断で尿酸値が高いと言われた」といった症状・お悩みに対して、専門的な視点から丁寧に診察いたします。
初診時には、症状の経緯や生活習慣について詳しくお話を伺い、血液検査による尿酸値や炎症反応のチェックを行います。
発作中の場合は炎症を抑える治療を、痛風と診断された場合は再発予防に向けた長期的な管理をご提案します。
また、痛風と似た症状を引き起こす他の関節疾患(リウマチ、偽痛風、化膿性関節炎など)との鑑別診断も重要です。当院では、視診や触診、必要に応じて他医療機関と連携した検査を通じて、原因を見極めたうえで適切な治療方針を立ててまいります。
「もしかして痛風かも?」「この痛みが何なのか不安」という段階でも構いません。
地域のかかりつけ医として、不安の早期解消と、再発のない生活をサポートする診療を心がけています。



当院では、痛風の治療を「急性期の対症療法」と「長期的な尿酸値コントロール」の両面から行っています。
まず、痛みや腫れが強い急性期には、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やコルヒチンを用いて炎症を抑える治療を行い、できるだけ早く日常生活へ戻れるようサポートします。
痛みが落ち着いた後は、再発予防のための尿酸値の管理を開始します。患者さまの体質や生活習慣、腎機能などを総合的に判断し、尿酸を下げる内服薬(尿酸生成抑制薬・排泄促進薬など)を適切に処方します。
必要に応じて定期的な血液検査を行いながら、無理なく続けられる治療を進めていきます。
さらに、痛風の再発を防ぐには日々の生活習慣が非常に重要です。当院では、食事・運動・水分摂取に関するアドバイスも積極的に行い、「患者さまご自身の力で再発を防げる」ようお手伝いしています。
「薬に頼りすぎたくない」「他院で治療を中断してしまった」といったお悩みにも対応可能です。
患者さま一人ひとりの背景に合わせたオーダーメイドの治療を大切にしていますので、どうぞ安心してご相談ください。



前野町つばめクリニックでは、痛風をはじめとする生活習慣病の診療において、「一時的な治療」ではなく「長く健康を守るサポート」を大切にしています。
痛風は、痛みが収まっても高尿酸血症が続いていれば、何度でも再発してしまう病気です。私たちはその特性を踏まえ、患者さまと一緒に将来を見据えた治療計画を立てていくことを心がけています。
「痛みをすぐに何とかしたい」「でも、薬だけに頼るのは不安」
そうしたお気持ちに寄り添いながら、ライフスタイルや体調の変化にも柔軟に対応できる診療を提供しています。
また、当院では「説明の丁寧さ」「相談しやすさ」「生活習慣の具体的な指導」にも力を入れています。
ご自身の健康に関心を持ち、前向きに取り組もうとされている方に対し、医師・看護師・スタッフがチームで継続的にサポートいたします。



「この痛み、もしかして…」と不安を感じたとき、あるいは「尿酸値が高いと言われたけれど放置している」という方も、まずは気軽にご相談ください。
「また元気に歩ける」「再発のない毎日を送れる」そんな未来のために、私たちが寄り添います。



〒174-0063
東京都板橋区前野町3丁目5-8 プレジール志村1階
03-5918-8718