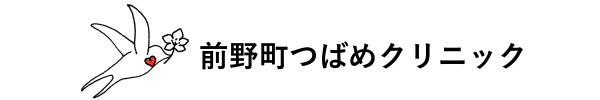糖尿病とは?
糖尿病とは?
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)濃度が高い状態が続く病気です。
私たちが食事から摂った糖分は、体のエネルギー源として利用されます。このとき、血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる役割を担っているのが「インスリン」というホルモンです。糖尿病になると、インスリンの分泌量が少なくなったり、うまく作用しなくなったりするため、ブドウ糖が細胞に取り込まれず、血液中にあふれてしまいます。この状態が「高血糖」です。
高血糖の状態が続くと、血管がダメージを受け、さまざまな合併症を引き起こすリスクが高まります。糖尿病は「自覚症状がほとんどない」ことが最大の特徴であり、放置しておくと、ある日突然、深刻な合併症を発症することがあります。
 糖尿病のチェックリスト~こんな方は糖尿病に注意~
糖尿病のチェックリスト~こんな方は糖尿病に注意~
糖尿病は初期には自覚症状が少ないため、ご自身で気づくのが難しい病気です。しかし、以下の項目に当てはまる方は、糖尿病のリスクが高いと言えます。
・家族に糖尿病の人がいる
・甘いものが好きで、間食が多い
・炭水化物(ごはん、パン、麺類など)をたくさん食べる
・肥満気味である
・運動する習慣がない
・喫煙の習慣がある
・健康診断で「血糖値が高い」と指摘されたことがある
これらの項目に当てはまる方は、一度医療機関での血糖値検査をおすすめします。早期に発見し、対策を始めることが大切です。
 糖尿病の症状
糖尿病の症状
糖尿病は初期には自覚症状がほとんどありませんが、血糖値がかなり高くなると、以下のような症状が現れることがあります。
・頻繁に喉が渇く
・尿の量が増え、トイレに行く回数が増える
・体がだるい、疲れやすい
・体重が急に減る
・傷が治りにくい
・手足がしびれる
これらの症状は、糖尿病以外の原因でも起こり得ますが、複数の症状が当てはまる場合は、一度ご相談ください。
 糖尿病の原因
糖尿病の原因
糖尿病は、大きく以下の3つのタイプに分けられます。
・1型糖尿病
自己免疫疾患などによって、インスリンを分泌する膵臓の細胞が壊されてしまい、インスリンがほとんど分泌されなくなるタイプです。比較的若年層に多く見られますが、年齢に関係なく発症することがあります。
・2型糖尿病
遺伝的な体質に加え、過食、運動不足、ストレスなどの生活習慣が原因で発症するタイプです。日本の糖尿病患者さんの大半がこのタイプです。
・その他の糖尿病
他の病気や薬の影響で血糖値が上昇するタイプです。
特に2型糖尿病は、生活習慣との関連が非常に強いため、生活習慣を見直すことが予防や治療の鍵となります。
 糖尿病の診断基準
糖尿病の診断基準
糖尿病の診断は、主に血液検査で行われます。以下のいずれかに該当すると、糖尿病と診断されます。
・HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の値が6.5%以上
・空腹時血糖値が126mg/dL以上
・75g経口ブドウ糖負荷試験で、2時間後の血糖値が200mg/dL以上
HbA1cは、過去1~2ヶ月の血糖値の平均を反映する数値で、診断や治療の経過観察に非常に重要な指標です。
 前野町つばめクリニックでの糖尿病治療
前野町つばめクリニックでの糖尿病治療
糖尿病の治療は、血糖値を適切にコントロールし、合併症を予防することが最大の目的です。患者さんの状態や糖尿病のタイプによって治療法は異なりますが、主に以下の3つを組み合わせて行います。
1. 食事療法
血糖値を管理する上で、食事療法は最も基本となる治療です。単に食べる量を減らすのではなく、栄養バランスを考え、適切なエネルギー量に調整することが重要です。当院では、管理栄養士と連携し、患者さん一人ひとりの食生活に合わせた無理のない食事プランを提案します。
2. 運動療法
適度な運動は、血糖値を下げるだけでなく、インスリンの働きを良くする効果もあります。ウォーキングなどの有酸素運動を中心に、患者さんの体力やライフスタイルに合わせた運動方法を提案します。
3. 薬物療法
食事療法や運動療法だけでは血糖値が十分に改善しない場合、薬物療法を開始します。飲み薬や、インスリン注射など、様々な治療法があり、患者さんの状態に合わせて最適なものを選択します。