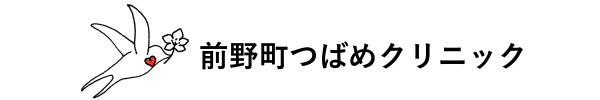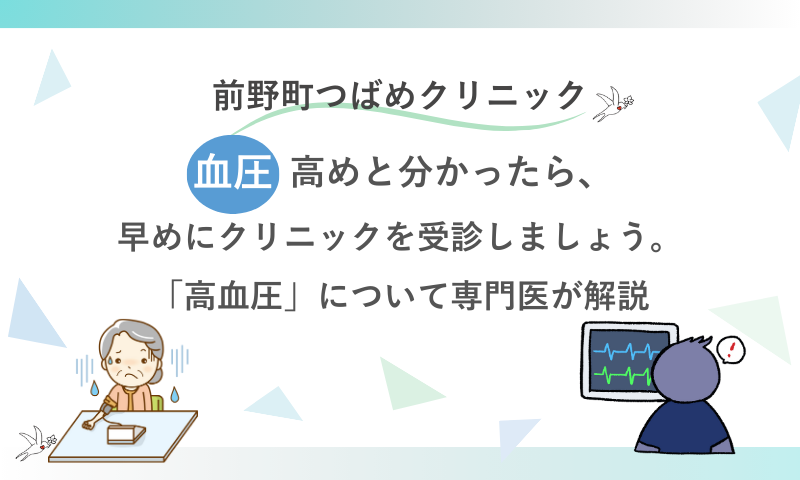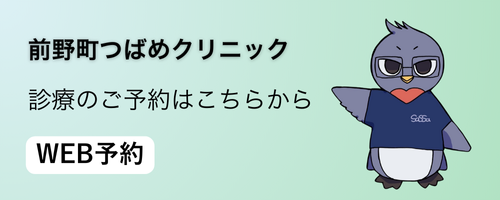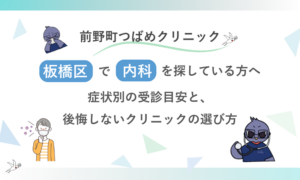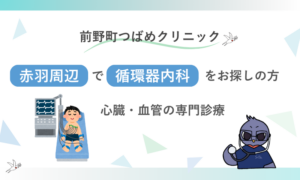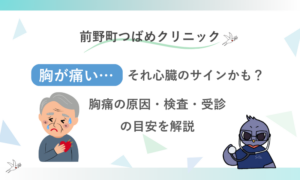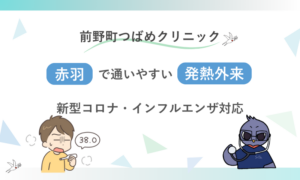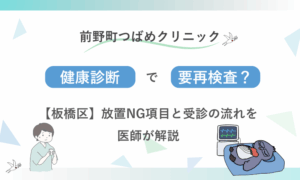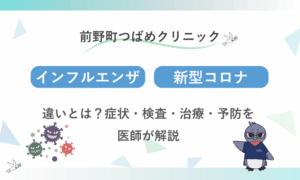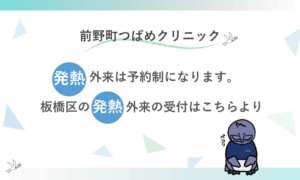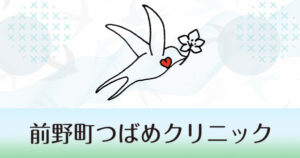「健康診断で『血圧が高めですね』と言われたけど、特に体調は悪くないし、何か対策をすべきなのかわからない…」
こんな風に思っている方は、多いのではないでしょうか。
高血圧は自覚症状がほとんどないため、放置してしまいがちですが、実は脳卒中や心筋梗塞などの重大な病気のリスクを高める要因になります。
日本では40歳以上の2人に1人が高血圧とされており、決して珍しいものではありません。しかし、「自分はまだ大丈夫」と思っているうちに症状が進行し、気づいたときには大きな病気につながることもあるのです。
一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態が続くと「高血圧」と診断されます。特に、塩分の多い食事や運動不足、ストレス、遺伝的要因などが重なると血圧が上がりやすくなります。
「高血圧って、結局どうすればいいの?」そう感じた方のために、この記事では高血圧の原因や症状、予防・改善方法について詳しく解説します。あなたの健康を守るために、ぜひ最後まで読んでみてください。
当院では、今症状がある方はもちろん、この先の不安や、過ごし方に迷う方も、当院でゆっくりと話して、少しでも安心を得ていただけるよう気軽になんでも相談していただける雰囲気づくりを心がけております。
【板橋区】前野町つばめクリニック院長



健康診断の結果に「血圧が高め」と書かれていても、「具体的にどういう状態なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
高血圧は、血管にかかる圧力が慢性的に高い状態を指し、そのまま放置すると血管や心臓に負担をかけ、重大な病気のリスクを高めることがわかっています。
高血圧の基準は?
一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態が続くと「高血圧」と診断されます。
血圧には個人差があり、一時的なストレスや運動後に血圧が上がることは珍しくありません。しかし、安静時の血圧が常に高い状態が続く場合、高血圧として注意が必要です。
どんな人が高血圧になりやすい?
高血圧は年齢とともに増える傾向があり、特に40代以降の方に多く見られます。また、以下のような生活習慣や体質の方は、血圧が上がりやすい傾向にあります。
| 塩分の多い食事をとる(味の濃い食事、加工食品の多用)運動不足が続いている(血流が悪くなり血圧が上がりやすい)肥満傾向がある(体重が増えると血管への負担が増加)ストレスをためやすい(交感神経が活発になり血圧が上昇)喫煙・過度な飲酒をしている(血管が収縮しやすくなる)家族に高血圧の人がいる(遺伝的要因も影響) |
高血圧を放置するとどうなる?
「特に症状がないし、大丈夫かな」と思っていると危険です。
高血圧は「サイレントキラー(沈黙の病気)」とも呼ばれ、気づかないうちに血管が傷み、動脈硬化が進行します。
これが原因で、時には、脳卒中や心筋梗塞などの重大な疾患につながりかねません。
「自分は大丈夫」と思わず、早めの対策や定期的な血圧チェックを心がけることが大切です。



高血圧は、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。しかし、血圧が高い状態が続くと、体にさまざまな影響が現れることがあります。
高血圧による主な症状
頭痛
特に朝起きたときに感じることが多い傾向があります。血圧の上昇により脳の血管が拡張し、圧力がかかることで痛みが生じます。
めまい・ふらつき
血圧の急激な変動により、脳への血流が不安定になりやすいくなり、めまいやふらつきを引き起こします。
動悸・息切れ
心臓が血液を送り出す負担が増加し、心拍数が上昇することで動悸や息切れを感じます。
耳鳴り
血圧の変化が内耳の血流に影響を与え、耳鳴りを引き起こします。
手足のしびれ
高血圧により血管が狭まり、末梢の血流が悪くなることでしびれを感じます。
これらの症状が現れた場合、高血圧が進行している可能性があります。特に頭痛やめまいが頻繁に起こる場合は、脳の血管に負担がかかっているサインかもしれません。
高血圧によるリスク
高血圧を放置すると、次のような重大な病気のリスクが高まります。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)
血圧が高い状態が続くと、脳の血管が詰まったり破れたりする可能性が高まります。
心筋梗塞・狭心症
心臓の血管が詰まりやすくなり、胸の痛みや心筋梗塞のリスクが上昇します。
腎不全
腎臓の血管が損傷し、腎機能が低下することで、最悪の場合透析が必要になることもあります。
動脈硬化
血管が固くなり、血流が悪くなることで全身の臓器に影響を及ぼします。
高血圧は単なる数値の問題ではなく、全身の健康に深刻な影響を与える可能性があるため、早めの対策が重要です。



高血圧の原因は大きく分けて「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の2種類があります。
本態性高血圧(原因が特定できないもの)
高血圧の約90%は、このタイプに分類されます。明確な単一の原因があるわけではなく、複数の要因が組み合わさって血圧が上がると考えられています。
主な要因として、以下のような生活習慣や体質が関係しています。
遺伝的要因
親や祖父母が高血圧の場合、遺伝的に影響を受ける可能性が高くなります。
塩分の過剰摂取
塩分を摂りすぎると、体内の水分量が増えて血圧が上昇します。
運動不足
血流が悪くなり、血管の柔軟性が低下することで血圧が上がりやすくなります。
肥満
体重が増えると心臓がより強い圧力で血液を送り出す必要があるため、血圧が上昇します。
ストレスの蓄積
ストレスが続くと交感神経が刺激され、血管が収縮して血圧が上がります。
加齢
年齢とともに血管の弾力が低下し、血流がスムーズに流れにくくなるため血圧が上がりやすくなります。
二次性高血圧(特定の病気が原因のもの)
全高血圧患者の約10%は、特定の疾患や薬の影響によって血圧が上がる二次性高血圧に分類されます。以下のような原因が考えられます。
腎臓の病気
腎機能が低下すると、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、血圧が上がります。
ホルモン異常
副腎ホルモンの異常分泌によって高血圧症になります。
甲状腺疾患
甲状腺ホルモンの過剰分泌により血圧が上がります。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中の呼吸停止が繰り返されることで、交感神経が活性化し血圧が上がります。
薬の影響
ステロイド剤、ピル、一部の鎮痛薬などが血圧上昇を引き起こすこともあります。
このような場合、原因となる疾患を適切に治療することで血圧が正常に戻る可能性があります。高血圧と診断された際には、単なる生活習慣病ではなく、何らかの疾患が隠れていないか医師と相談することが大切です。



高血圧は、日々の生活習慣を見直すことで予防できます。以下のポイントを意識して、血圧を正常に保ちましょう。
塩分を控える
日本人は塩分を摂りすぎる傾向にあります。1日の塩分摂取量の目標は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。減塩のコツとして、「醤油や塩の使用量を減らす」「加工食品を控える」ことを心がけましょう。
適度な運動を取り入れる
運動は血流を改善し、血圧を安定させる効果があります。特におすすめなのは、「ウォーキングやジョギング(1日30分程度)」「ヨガやストレッチでリラックス効果を高める」「軽い筋トレで基礎代謝を上げる」ことです。無理のない範囲で継続することが大切です。
ストレスを溜め込まない
ストレスが続くと交感神経が活発になり、血圧が上がります。リラックスする時間を意識的に作り、趣味やリフレッシュできる時間を確保しましょう。深呼吸や瞑想を取り入れたり、十分な睡眠を確保することを心がけましょう。
高血圧は「予防」が重要です。毎日の小さな積み重ねが、健康な未来を作ります。



“健診で高血圧を指摘された方で、無症状で高血圧緊急症を疑う初見のない方は、まずは家庭血圧の計測をお勧めしています。
やはりクリニックや健診会場では無意識に血圧が上がってしまう白衣高血圧の方がそれなりの割合でいらっしゃるからです。
2週間を目安に家庭での血圧を計測いただき、その結果を確認して高血圧の有無の診断を行います。



心臓病、脳卒中、腎臓病、その他血管疾患の既往がある方や、その兆候が疑われる方は、優先的に内服での治療の開始をお勧めしています。原病の増悪予防につながるため、早めの内服開始のメリットが大きいからです。
他方そのような既往のない、無症状の方には高血圧の程度にはよりますが、なるべくは食事・運動療法での改善を促します。特に他に内服されていない方にとっては、1日1回でも長期的に内服するということは、生活の質に大きく関わってくると考えているからです。
とはいえ、食事・運動療法でも効果が乏しく、いつまでも高血圧を放置することも患者さんにとってはリスクになりますので、食事運動療法でなるべく早期に結果が出るように、一人ひとりに効果的と思われる方法を提案しています。食事運動療法を一定期間行っても効果が乏しい方に対しては、その時点で内服療法の開始を提案します。
内服開始後も、食事運動療法を継続し、投薬量は必要最低限で済むように、可能なら内服を修了できるように、患者さんとクリニックで二人三脚の治療を行っています。



高血圧は無症状のことが多いので、放置されがちですが、放置することで重篤な疾患を引き起こすリスクが跳ね上がります。
他方、世界中で高血圧の治療をされる方は、非常に多く、新しい治療法やデータもどんどん更新されていきます。
患者さんの生活の質を下げずに、安全な健康管理が行えるよう、いつも患者さん一人ひとりに最適な治療法を提供できるよう用意しています。
高血圧が少しでも気になっている方は、お気軽にご相談ください。



〒174-0063
東京都板橋区前野町3丁目5-8 プレジール志村1階
03-5918-8718